
カメラのピントを合わせるとき、あなたはどちらの目で覗きますか?
普段何気なく使っている手足と同様に、実は私たちにも「利き目」があることをご存知でしょうか。日本人の実に約70%は右目が[利き目]といわれています。
「利き目」が私たちの身体にどのような影響を与えているのか、詳しく見ていきましょう。
そもそも「利き目」って何?
 私たちは普段、両目で物を見ていますが、実は脳はどちらか一方の目から得られる情報を優先的に処理しています。この優先的に使われる目を「利き目」、または専門用語で「優位眼」と呼びます。
私たちは普段、両目で物を見ていますが、実は脳はどちらか一方の目から得られる情報を優先的に処理しています。この優先的に使われる目を「利き目」、または専門用語で「優位眼」と呼びます。
「利き目」は、手や足に「利き手」や「利き足」があるように、人によってそれぞれ異なります。一般的に、右利きの人の約70%は右目が、左利きの人の多くは左目が「利き目」であるといわれています。日本人の約9割が右利きであることから、「利き目」も右目である人が多いとされています。筆者の聞き手は右ですが、「利き目」は左であり、このように「利き目」と「利き手」が逆という人は全体の約10%ほどといわれています。
「利き目」が身体に与える影響
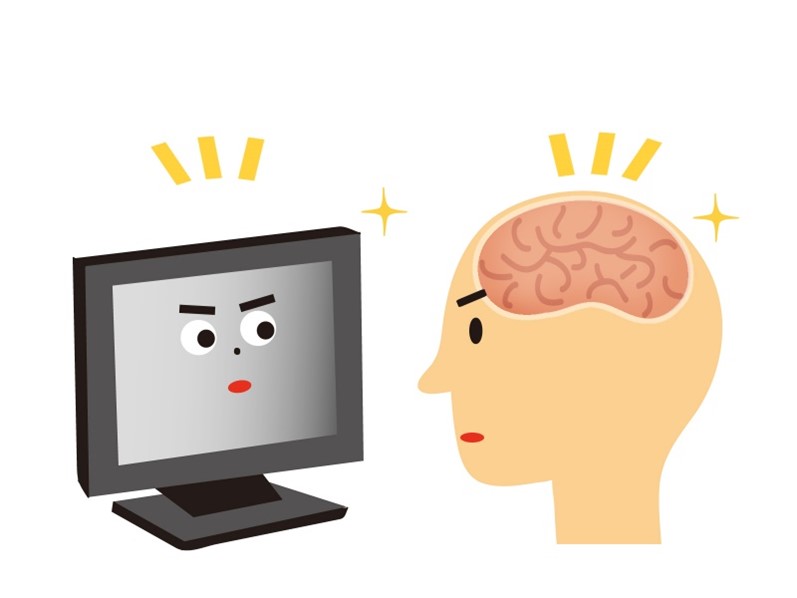 「利き目」は、姿勢の歪みと筋肉の緊張に大きく影響を及ぼしています。「利き目」があることで、身体が自然と特定の方向に傾きやすくなります。たとえば、「利き目」が左目の方の場合、身体が左側に傾く傾向があり、これを長年の積み重ねることによって姿勢の歪みにつながります。
「利き目」は、姿勢の歪みと筋肉の緊張に大きく影響を及ぼしています。「利き目」があることで、身体が自然と特定の方向に傾きやすくなります。たとえば、「利き目」が左目の方の場合、身体が左側に傾く傾向があり、これを長年の積み重ねることによって姿勢の歪みにつながります。
姿勢が歪むと、身体の特定の部位に負担がかかり、筋肉が過度に緊張しやすくなります。特に、首や肩の筋肉は、利き目によって常に同じ方向に力が入るため、こりや痛みを感じやすくなります。
また、「利き目」ばかりを優先的に使うと、眼精疲労を引き起こす可能性が高まります。常に同じ目ばかりを使うことで、目の筋肉が疲労し、視力低下や頭痛などの症状が現れることがあります。
もし、「利き目」に白内障などの病気が起こってしまった場合、日常生活に大きな支障が出てしまう可能性があります。たとえば、運転や細かい作業がしにくくなるなど、生活の質が大きく低下してしまうことがあります。また、斜視や弱視といった目の病気の治療では、どちらの目が「利き目」かによって治療法や効果が大きく変わってきます。「利き目」は、私たちが普段意識することは少ないかもしれませんが、視力や生活の質に大きく影響を与える重要な要素なのです。
簡単にできる!あなたの「利き目」のチェック方法

では、自分の「利き目」がどちらなのか、簡単に確かめる方法を見ていきましょう。
1)筒や輪を作る方法
両手で筒や小さな輪を作ります。遠くの目印(黒丸や対象物)をこの筒や輪の中に見ます。そして、右目と左目を交互に閉じます。筒や輪の中に目印が残っている方が「利き目」です。
2)指差し法
まずは、離れた場所にあるものを見ます。そのものを指差したまま、右目と左目を交互に開閉します。ズレずにしっかり指を差して見えている方が「利き目」です。
3)三角形法
はじめに、両手で小さな三角形を作ります。約3メートル離れた対象物を三角形の中に入れます。左右の目を交互に閉じます。対象物を見続けることができる方の目が「利き目」です。
この他にも、カメラをかまえた時、どちらの目で見ているのかでも「利き目」を簡単に判断できます。
スポーツや仕事で知っておきたい!「利き目」の活かし方
 「利き目」がわかったところで、一体何に活かせるの?と思ったあなた。
「利き目」がわかったところで、一体何に活かせるの?と思ったあなた。
「利き目」がわかればスポーツや仕事のパフォーマンスを向上させることができるかもしれません。たとえば、野球やバスケットボールでは、「交差性」と呼ばれる、「利き目」と「利き手」が反対の選手が有利であるといわれています。「利き手」と「利き目」が反対の場合、より広い視野でボールを捉えられ、変化球にも対応しやすくなります。反対に射撃では、「利き目」と引き金を引く手が同じであることが重要です。「利き手」と「利き目」が同方向であることで、自然な姿勢で照準を合わせることができ、長時間競技でも疲労を軽減できます。また、ゴルフスイングでは、「利き目」に合わせた顔の向きが重要です。たとえば、右目が「利き目」の場合、バックスイング中に顔をあまり動かさず、右目でボールをしっかり見ることでミート率が向上する可能性があります。
スポーツだけでなく、仕事面においても「利き目」を意識することが大切です。重要な情報や作業スペースは、「利き目」側に配置することで、効率的に作業を行うことができます。また、複数のモニターを使用する場合、メイン画面を「利き目」側に配置すると、情報をより素早く処理できます。
「利き目」を理解して、日々の生活に活かそう

自分の「利き目」を把握することで、視覚の使い方や体のバランスを意識しやすくなります。スポーツや仕事、日常生活の中で「利き目」を活かせば、動作がスムーズになったり、目の負担を軽減したりすることが可能です。「利き目」を上手に活用して、より快適で効率的な生活を送りましょう。
